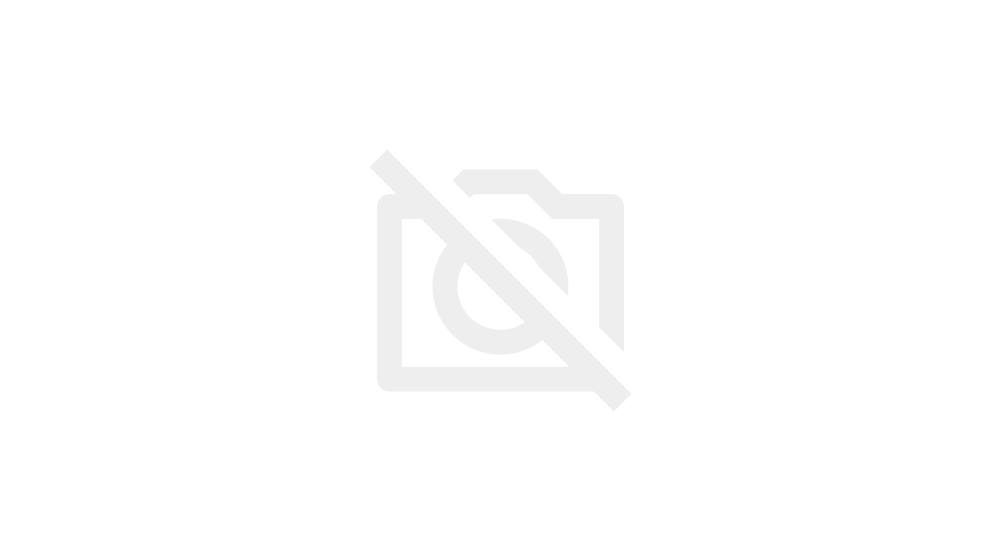実務重視型の科目選択
税理士としての実務を考えた場合次の科目選択が最強です。理由は次のとおりです。 ( ) + + + 必須科目 選択必須 まず、法人税法の知識は実務で頻繁に使います。税理士として必須なため絶対に外せません。 次に開業税理士にとって一番大きな訴訟リスクが消費税法の届出関係の失念となっているため実務を考えた場合には消費税法も絶対に外せません。しかも消費税の申告は法人と個人事業者両方に関わってきます。しかも赤字企業であっても消費税の納税が発生するのが通常です。また免税事業者であっても事業 ...
財務諸表論
財務諸表論の学習内容、財務諸表論短期合格のコツ 財務諸表論はいわゆる財務会計に関する理解度を問う試験となっており、簿記論と同様に、税理士として業務をする上での基礎中の基礎であり必須科目となっています。近年合格率が20%くらいとかなりの高い水準を維持しておりかなり楽に合格できる科目となっています。 試験問題は理論50点、計算50点で構成されており、計算問題は簿記論と重複する部分がかなり多いですが、財務諸表論ではより財務諸表の作成という点に比重を置いて表示や区分等についての学習も必要となります。 理論に関して ...
簿記論
簿記論の学習内容、簿記論短期合格のコツ 簿記論は税理士として業務をする以前に経理実務の基礎中の基礎です。複式簿記が分からないと経理実務もできません。したがって税理士試験において必須科目となっています。 試験形式としては計算問題のみで税理試験の科目としては唯一理論がありません。計算は個別問題と決算修正型の総合問題等で構成されています。 会計基準の改正等により年々学習内容が高度になっています。年によってが合格確実ラインの特典が100点中20数点の年度もあったりするようです。しかし受験生のレベル自体はまだまだ低 ...
国税徴収法
国税徴収法 国税徴収法は申告された国税が納付され負かった場合の滞納処分などの手続の執行について必要な事項を定めている法律です。税理士試験の出題としては例年理 論だけの出題が続いており、合格するためには民法などの法律の知識が必要となります。したがって法学部出身の方には大きなアドバンテージとなります。 税理士試験に関する最新の情報 税理士試験に関する最新の情報に関しましてはTACと資格の大原それぞれの学校から資料を請求してご確認ください。受験指導のプロですのでそのほうが間違いもありません。資 ...
事業税
事業税 事業税は事業者に対して課される税金です。事業税には個人事業税と法人事業税があります。法人事業税にはやや話題性の高い外形標準課税が数年前から導入さ れており、税理士として実務をする上での使用頻度はそれなりに高いです。本試験では理論70点計算30点と理論に比重が置かれています。 税理士試験に関する最新の情報 税理士試験に関する最新の情報に関しましてはTACと資格の大原それぞれの学校から資料を請求してご確認ください。受験指導のプロですのでそのほうが間違いもありません。資料を請求する場合 ...
住民税
住民税 住民税、事業税、固定資産税は地方税法を根拠法とする地方税です。住民税には個人住民税と法人住民税がありますが過去の本試験ではほとんどが個人住民税の みの出題となっています。法人税法や所得税法との関連が高いため学習をする場合にはこれらと同時に、またはこれらを学習した後にするのが理想的です。 税理士試験に関する最新の情報 税理士試験に関する最新の情報に関しましてはTACと資格の大原それぞれの学校から資料を請求してご確認ください。受験指導のプロですのでそのほうが間違いもありません。資料を ...
消費税法
消費税法 消費税法は1989年から税理士試験の受験科目となっておりまだまだ歴史が浅く、条文数も少ないです。また簿記論財務諸表論に合格した受験生の大半が最初に受験する税法科目であるため、税法科目の中では比較的受験生のレベルも低く合格しやすい科目といえます。 ただし近年の税制改正により納税義務判定がかなり複雑化したりリバースチャージという仕組みが創設されたりとどんどん難易度が高くなってます。したがって近年の学習のボリュームはかなり多くもはやミニ税法とは呼べないレベルに難易度が上がってます。 なお、消費税法は届 ...